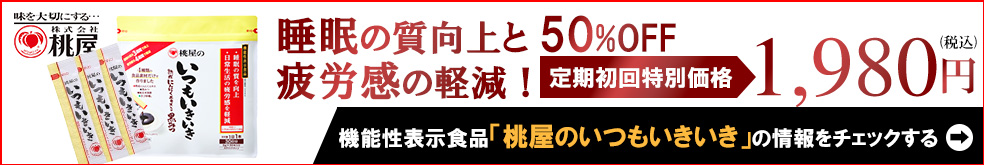目次
ちゃんと眠れていないかも?眠りが浅い人の特徴

「しっかり寝ているはずなのに、なぜかスッキリしない…」そのような場合は、眠りが浅い可能性があります。眠りが浅い人の特徴としては、以下の4つがあげられます。
✓ 寝ても疲れが取れない
✓ 集中力が低下している
✓ 怒りっぽい
✓ 体調を崩しやすい
寝ても疲れが取れない
眠りが浅い人は、熟睡できていないために疲れが取れず、朝起きたときに気力も体力もわきにくい傾向にあります。
本来、質の良い睡眠がとれていれば成長ホルモンが分泌され、日中にダメージを受けた身体の修復が行われます。しっかり睡眠をとることで、疲労回復ができるのです。
しかし、睡眠の質が悪いと成長ホルモンが十分に分泌されず、疲労回復がスムーズに行われないため、疲れを感じやすくなります。
集中力が低下している
眠りが浅い人は日中眠気が残ってしまい、集中力や注意力が低下して仕事や勉強で良いパフォーマンスを発揮できないことがあります。
例えば、集中力が持続せずにケアレスミスが増えたり、仕事や家事、勉強にかかる時間が長くなったりと、作業効率が悪化している一面がみられます。
怒りっぽい
睡眠不良のときには、意欲や感情の制御、集中力や注意力、判断力などを司る前頭葉がダメージを受けて、脳活動が極端に低下するといわれています。
怒りっぽい、感情の起伏が激しいというのも眠りが浅い人の特徴のひとつです。
体調を崩しやすい
睡眠が十分に取れない状態が続くと、自律神経のバランスが崩れやすくなり、さまざまな体調不良を引き起こすことがあります。
特に影響を受けやすいのが消化器系で、下痢や便秘、吐き気といった症状が表れることがあります。
また、自律神経の乱れは血液循環の悪化やホルモンバランスの乱れも招きがちです。
最近体調が悪いと感じる場合、眠りが浅くなっているのかもしれません。
眠りが浅い状態を放置するリスク

続いて、眠りが浅い状態を放置することで心身にどのような影響が及ぶのか解説します。
記憶力の低下を招く
眠りが浅い状態が続くと、記憶力が低下することがあります。
脳にある「海馬」は記憶の司令塔とも呼ばれ、新しい記憶を一時的に保管し、必要な情報を整理して大脳皮質に長期記憶として保管する役割を担っています。
しかし、睡眠が不足すると海馬が縮小することがあり、記憶力に悪影響をおよぼす可能性があるのです。
食欲に関わるホルモンのバランスが崩れる
浅い眠りが続くと、食欲をコントロールするホルモンのバランスにも影響がおよびます。
睡眠時間が短くなると、食欲を抑えるホルモン「レプチン」の分泌が減少し、食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌が増加します。
その結果、食欲が増して食べすぎや間食が増えやすくなり、体重増加や肥満のリスクが高まってしまうのです。
眠りが浅くなる3つの原因

眠りが浅くなってしまう原因として、主に以下の3つがあげられます。
・ストレスによるもの
・病気によるもの
・生活習慣や環境によるもの
それぞれひとつずつ解説します。
1.ストレスによるもの
眠りが浅くなる原因のひとつに、ストレスがあげられます。ストレスが溜まっていると、自律神経のバランスが乱れ、不眠につながることが多いです。
自律神経には、心身を活発させる「交感神経」と心身をリラックスさせる「副交感神経」の2種類があります。
通常、日中は「交感神経」が優位になり、夜にかけて「副交感神経」が優位にはたらくようになっています。睡眠中は副交感神経が優位になっていると、質の良い睡眠が取りやすいです。
しかし、過度なストレスを抱えていると交感神経が優位になってしまい、眠れなくなったり、睡眠の質が低下したりしてしまうのです。
特に、神経質な人や生真面目な人はストレスをより強く感じやすく、それが原因となり不眠症になりやすい傾向にあります。
2.病気によるもの
眠りが浅くなる原因のひとつに、病気や身体の不調が隠れていることがあります。
睡眠時の呼吸について家族に指摘されたり、脚のむずむず感や痛み、かゆみなどで眠れなかったりする場合、睡眠障害が原因かもしれません。
こうした不調が続き、日常生活に支障をきたしているようであれば、医療機関の受診を検討しましょう。
3.生活習慣や環境によるもの
普段から口にしているものや何気ない生活習慣が、睡眠の妨げになっていることもあります。
例えば、コーヒーや紅茶などに含まれるカフェインやアルコールには覚醒作用があるため、就寝前に摂取してしまうと睡眠の質を低下させるおそれがあります。
また、就寝前にPCやスマートフォンが放つブルーライトを浴びると、脳が昼だと勘違いしてしまい、交感神経が優位になるので寝つきが悪くなることがあるので注意が必要です。
さらに、昼夜交代制の勤務シフトや時差などは体内時計が乱れてしまい、眠れない原因となります。
そのほかにも、ベッドや枕などの寝具が合わない、寝室の温度、湿度が適切に設定されていないことも、睡眠の質を下げる要因となります。
深い眠りを得るためのポイント

ここでは睡眠の質を向上させるためのポイントを解説します。
生活習慣を改善していけば、質の良い睡眠が取れるようになります。具体的にどのような点に気を付ければ良いのか、詳しく見ていきましょう。
睡眠環境を整える
質の高い睡眠をとるためには、まず「眠りやすい環境づくり」が欠かせません。
寝具や室温、照明など、睡眠環境を整える具体的なポイントを紹介します。
自分に合った寝具を使う
就寝中の快適さを保つために、吸湿性や放湿性に優れ、体型に合った寝具を選びましょう。
特に、後頭部から首、胸、胸から腰にかけてのS字カーブをバランス良く支える寝具は快眠につながります。
枕の高さが合っていないと、起床時に首や肩のこり、胸の筋肉の緊張が残ることがあります。首のカーブの角度を専門店で計測してもらい、適切な高さの枕を選ぶのがおすすめです。
また、敷き布団やベッドマットは、柔らかすぎると腰に負担がかかり、硬すぎると骨が当たって痛みや血流の悪化を招くおそれがあります。
店頭で実際に横になって寝心地を確かめ、身体に合った適度な硬さのものを選びましょう。
適切な温度を保つ
快適な睡眠を得るためには、寝室の温度と湿度のバランスを保つことも重要です。
エアコンや加湿器を活用し、季節に合わせた環境を整えましょう。室温は夏で26℃前後、冬で20℃前後、湿度は40~60%程度を保つのが良いとされています。
照明はやわらかい色にする
体内時計は光によって調整されており、夜間に明るい照明の中で過ごすと寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするおそれがあります。
睡眠の質を高めるためには、就寝1~2時間前から暖色系のやわらかな照明に切り替え、少しずつ明るさを落としていくのがおすすめです。
寝室はもちろん、リビングや浴室など、就寝前に過ごす空間の照明も控え目にすることで、体内時計に「そろそろ寝る時間」と知らせる合図になります。
入浴で寝つきを良くする
湯船に浸かることも睡眠の質を向上させるのに効果的です。
入浴することで一時的に深部体温が上がり、上昇した体温が低下してくるときに眠気が訪れるようになります。そのため、入浴は就寝の1〜2時間前を目安に行いましょう。
おすすめは、38〜40℃のぬるめのお湯で、25〜30分を目安に浸かることです。42℃以上の熱すぎるお湯は交感神経を優位にしてしまうため、注意しましょう。
起きたら自然の光を浴びる
太陽光は、体内時計を正しい時間に調整するはたらきがあります。人の体内時計の周期は24時間より長めにできているため、体内時計を毎日調整していかないと、段々と生活リズムが後ろにズレてしまいます。
体内時計を調整するためには、起床直後に太陽光を浴びることが大切です。そのため、起きたらまずはカーテンを開けて、自然の光を部屋の中に取り込むようにしましょう。
ただし、夜に強い照明を浴びすぎると、体内時計がズレてしまって起床の妨げになることがあるので、就寝前の照明には注意してください。
食生活を改善する
日頃の食生活を改善することで、睡眠の質の向上が期待できます。
忙しくて朝食を抜く方も多いかもしれませんが、朝食はしっかり摂ることが大切です。栄養バランスの取れた朝食は身体を目覚めさせ、睡眠と覚醒のリズムにメリハリをもたらします。
夕食は就寝3時間前までに済ませるのが理想です。就寝直前に食事を摂ると消化活動が優先され、眠りが浅くなったり翌日に疲れが残ることがあります。
また、睡眠の質を高めるなら、トリプトファンを積極的に摂取しましょう。トリプトファンは必須アミノ酸の一種で、睡眠ホルモンである「メラトニン」を作り出すのに欠かせない材料です。
トリプトファンは体内で合成できない成分であるため、食事から摂る必要があります。主に肉や魚、豆腐や納豆などの大豆製品、チーズや牛乳などの乳製品、卵やナッツ類などに豊富に含まれています。
朝にトリプトファンを摂取すると、夜に眠りやすくなるため、朝食のメニューに玉子焼きや納豆、焼き魚などを取り入れてみると良いでしょう。
睡眠の質を上げる食べ物については、以下の記事でも詳しく解説しています。
「睡眠の質を上げる食べ物とは?意識的に摂りたい栄養素を紹介」
適度に運動をする
質の良い睡眠のためには、適度な運動を日常に取り入れることも大切です。
運動は午前中よりも午後に行うのが効果的とされており、軽く汗ばむ程度の活動が理想です。無理のない運動によって心地良い疲労感が得られ、自然と眠気が促されます。
ただし、寝る前の激しい運動はかえって寝つきを悪くしてしまうこともあるため、注意が必要です。ウォーキングやストレッチなど、負担が少ない有酸素運動を継続しましょう。
就寝前のアルコール、カフェインは控える
就寝直前は覚醒作用のあるアルコールやカフェインを含む飲み物(コーヒー、緑茶、紅茶など)を口にするのは控えましょう。
特に、アルコールは一時的に寝つきを良くしてくれるものの、利尿作用を持っているため、眠りを妨げてしまうおそれがあります。
ストレスを溜めない
眠りにとってストレスは大敵です。ストレス発散法としては、以下のものがあげられます。
・おいしいものを食べる
・映画を見る
・好きな音楽を聴く
・読書をする
・旅行に行く
自分に合った趣味を見つけて気分転換をし、ストレスを溜めないように工夫しましょう。
また、適度な運動も、ストレス発散にはおすすめです。短時間で激しい運動をするというよりは、軽く汗ばむ程度の有酸素運動などの運動習慣を作ることで心地良い睡眠リズムを作ることができます。
眠りが浅い人に試してほしい「桃屋のいつもいきいき」
眠りの浅さや疲れが気になる方は、睡眠の質と疲労感の軽減に着目した機能性表示食品「桃屋のいつもいきいき」を取り入れてみてはいかがでしょうか。
「桃屋のいつもいきいき」には、酸化ストレス(※)にアプローチできる熟成にんにくエキスが含まれており、すっきりとした目覚めと健康的な毎日をサポートします。
黒みつ味で飲みやすく、熟成効果によりにんにく特有の匂いもマイルドに抑えられています。1日1回、ホットミルクやヨーグルトに混ぜて手軽に続けられるのも魅力のひとつです。
「睡眠をしっかりとっているのに、翌朝まで疲れが残っている」「睡眠の質を上げたいけど、できるだけ薬に頼りたくない」という方は、ぜひ「桃屋のいつもいきいき」をお試しください。
※酸化ストレス…身体的、精神的なストレスがかかると、体内で活性酸素が発生します。これが増えすぎると酸化ストレスが溜まり、睡眠の乱れや疲労感の原因となります。
まとめ
眠りが浅いと、疲れが取れなかったり、日中のパフォーマンスが下がったりしてしまうおそれがあります。
もしぐっすりと眠れない日々が続いている場合は、リフレッシュをしたり、食生活を見直したりするなどして、心身ともに健康的な生活を心がけてみましょう。