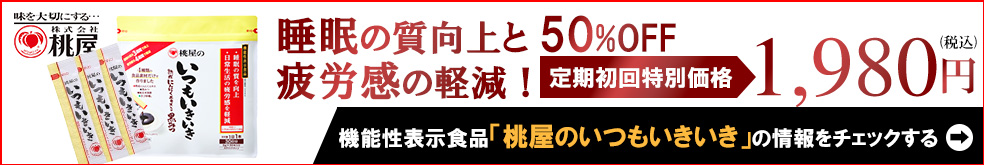50代男性の疲れが溜まっているサイン

50代の男性は、身体や心に疲れが溜まりやすくなります。
以下の身体のサインに心当たりがある方は、特に疲労が溜まっている証拠です。まずは自分の状態をチェックしてみましょう。
✓ 日常的な倦怠感や身体の重さを感じる
✓ 寝つきが悪い、起きるのが辛い
✓ 日中の眠気が強い
✓ 気力や集中力が続かない
✓ 気分が沈み、やる気が出ない
✓ 注意力が散漫になり、ミスが増える
✓ お酒の量が増えた
✓ 肩こりや目の重さを感じる
✓ 顔色が優れない
✓ 肌が乾燥している
当てはまる項目が多いほど、心身の回復が必要な状態といえます。
また、調子を崩す頻度が増えているのに放置していると、回復も難しくなります。早めのケアをして、心身をいたわりましょう。
50代男性の疲れがとれない原因

いつもより疲れを感じるのには、原因があることがほとんどです。次に、50代男性が疲れがとれないと感じる主な原因を6つに分けて解説します。
原因1|ストレスの蓄積
日常生活でさまざまなストレスが積み重なると、身体に負担がかかります。
下記は、主なストレスの種類とその原因です。
| ストレスの種類 | ストレスの原因 |
| 身体的ストレス | ・過度な労働
・激しすぎる運動 |
| 心理的ストレス | ・仕事のプレッシャー
・家庭内のトラブル |
| 物理的ストレス | ・気温の変化
・騒音や光の刺激 |
| 生物的ストレス | ・季節性の花粉
・ウイルスや細菌感染 |
| 化学的ストレス | ・化学薬品
・排気ガス |
原因2|睡眠の質の低下
睡眠の質が低下すると身体が十分に回復できず、疲れが蓄積しやすくなります。
睡眠中は、レム睡眠とノンレム睡眠の2つの状態を繰り返します。
レム睡眠とは、身体は休んでいるものの脳は活動している状態です。このとき、記憶の整理や定着が行われています。
一方、ノンレム睡眠時は、大脳が休息している状態です。睡眠中は副交感神経が優位になり、深いノンレム睡眠を経て細胞機能が修復され、心身の疲れが解消されます。
しかし、睡眠の質が悪化すると、交感神経が優位のままとなり、細胞が本来の機能を果たせなくなります。
例えば、睡眠中のいびき、発汗、頻繁に目が覚めるなどの場合には、睡眠の質が低下しているサインです。
原因3|食生活の乱れ
食生活が乱れると、1日の活動に必要なビタミンやミネラルなどの栄養素が不足し、疲れやすくなります。
下記に、主な栄養素と疲れの関係をまとめました。中でも、不足しやすいのはたんぱく質、ビタミンB1、鉄分といわれています。
| 栄養素 | 疲れとの関係 |
| 糖質 | 不足するとエネルギー不足により、疲れやすくなる |
| たんぱく質 | 不足するとアミノ酸が低下し、細胞や筋肉の修復が遅れ、脳内物質やホルモンの生成も不十分になるため疲労につながる |
| ビタミンB1 | 糖質をエネルギーに変えるために必要で、不足すると食欲不振や疲労が起こる |
| ビタミンB2 | 脂質をエネルギーに変える際に必要で、不足すると疲労感が増す |
| ビタミンB6 | アミノ酸の代謝を助ける補酵素として、疲労回復に重要な役割を果たす |
| 鉄分 | 血液中のヘモグロビンの構成成分として酸素を運ぶため、不足すると貧血や倦怠感が生じる |
普段の食生活を見直し、不足している栄養素がないか確認してみましょう。
原因4|脳への負荷
脳の酷使によって負荷がかかることも、身体の疲れを強める原因です。
日本では慢性的な疲労が問題視されており、厚生労働省の調査によると、50代の約3割が「睡眠で休養を十分にとれていない」と答えています。
また、日本では週に49時間以上働いている長時間労働者が多いという現状もあります。
人間関係や業務内容にストレスを感じていなくても、長時間労働をしている場合は疲れが溜まりやすいため、早めに対処することが重要です。
出典:厚生労働省「平成30年 国民健康・栄養調査報告」「我が国における時間外労働の現状」
原因5|運動不足
運動不足になると、代謝が低下し血流が悪化します。身体に蓄積された疲労物質を排出しにくくなり、結果的に疲れやすくなるのです。
特にデスクワークで長時間同じ姿勢を保つことが多い方は、さらに血液の流れが悪くなる傾向があります。
このような状態が続くと、疲れが蓄積してしまいます。運動不足によって筋力が低下すると、普段の歩行や姿勢維持にも体力を消耗しやすくなるため改善が必要です。
原因6|男性ホルモンの減少
男性ホルモン「テストステロン」の分泌量は20~30代でピークに達し、それ以降は加齢とともに緩やかに減少します。この影響により、心身にさまざまな不調が表れる場合があります。
例えば精神面では気分が沈む、やる気が出ない、記憶力や集中力が低下する、よく眠れないなどの症状がみられます。
身体面では、ほてりやのぼせ、頭痛のほか、疲労感や疲れやすさも招きがちです。
また、テストステロンには筋肉を増やし体脂肪を減らす作用があるため、分泌量が減少すると体重・体脂肪の増加やLDL(悪玉)コレステロールの上昇を招くリスクも高まります。
なお、テストステロンの低下は加齢のほか、ストレスや生活習慣も要因となります。
50代男性におすすめする疲労回復の方法

50代の男性が抱える疲れを解消するためには、日常生活に取り入れやすい疲労回復の方法を選ぶことが重要です。
ここでは、効果的な方法を5つ紹介します。
方法1|ゆっくりと入浴する
入浴は、身体を温めることで筋肉の緊張をほぐし、血流やリンパの流れを改善する効果があります。体内の老廃物が流れやすくなり、疲労回復につながります。
長時間の入浴や高温のお湯は逆に身体を疲れさせてしまうこともあるため、38度程度のぬるめのお湯に25~30分程度ゆったりと浸かることが理想です。
方法2|質の高い睡眠をとる
睡眠は、身体や脳の疲労回復に欠かせません。
十分な睡眠時間を確保することはもちろん、睡眠の質にも気を配ることで、より効果的に疲労を回復できます。
・日中に適度な運動を行う
一駅分歩く、エスカレーターではなく階段を使うなどでもOKです。
・食後すぐの就寝を避ける
消化に時間がかかるため、寝る1〜2時間前には食事を済ませましょう。
・湯船に浸かって身体を温める
リラックスでき、睡眠に入りやすくなります。
・就寝前のアルコールやカフェインを控える
覚醒してしまうため、アルコールやカフェインが入っていないものを選びましょう。
・就寝前スマートフォンやPCを操作しない
強い光を浴びることで目が冴えてしまうため、少なくとも寝る1時間前には操作しないようにしましょう。
関連記事:「朝までぐっすり寝る10の方法!快眠のツボ・ストレッチも紹介」
方法3|食事で栄養を補給する
バランスの良い食事は、疲労回復においても重要です。
特に、下記の食材を意識して摂取することで、疲れの予防や回復を図ることができます。
| 食材 | 含まれる栄養素 |
| 牡蠣 | 亜鉛、ビタミンB12など |
| うなぎ | ビタミンA・B1・B2・E・Dなど |
| 青魚(鰹、鯖、まぐろなど) | ビタミンB6・B12、ナイアシンなど |
| 豚肉 | ビタミンB1・B6、ナイアシンなど |
参考:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
ただし、疲労回復のためには、特定の栄養素だけ摂取していれば良いわけではありません。栄養素は互いに助け合い、影響し合うことで効果を発揮します。
そのため、さまざまな栄養素を組み合わせたバランスの良い食事を心がけましょう。
関連記事:「精のつく食べ物とは?疲れ知らずのスタミナをつけよう!」
方法4|サプリメントを併用する
毎日のバランスの良い食事に加えて、サプリメントを併用するのもおすすめです。
なかでも疲労感の軽減に役立つのが、酸化ストレスを減らす抗酸化物質です。酸化ストレスは、体内で発生する活性酸素が増えすぎることで生じます。
活性酸素には体内で細菌やウイルスを撃退する役割があり、通常は抗酸化物質によって取り除かれます。しかし、抗酸化物質で消去しきれないほど多くの活性酸素が発生すると酸化ストレスが溜まり、疲労感につながるのです。
「桃屋のいつもいきいき」は、この酸化ストレスの軽減に着目し、疲労感を軽減する機能性表示食品です。
抗酸化作用のある熟成にんにくエキスが酸化ストレスを軽減し、疲労感と睡眠をダブルでサポートします。臨床試験においても、「睡眠の質向上」「疲労感の軽減」の2つの機能を有することが明らかになっています。
熟成効果でにんにく独特のにおいが抑えられているため、毎日の食事に取り入れやすいのも特徴です。
「疲れやすいと感じる」「朝起きても疲労感が残っている」とお悩みの方は、ぜひ下記から詳細をご覧ください。
方法5|軽い運動をする
軽い運動は疲労対策に効果的です。運動によって体内の血流が改善され、疲労物質が体外へ排出されることで疲労回復が促進されます。
ただし、激しい運動は逆効果になることがあるため、散歩やウォーキングなどの有酸素運動を行いましょう。自宅でストレッチのような軽い運動を取り入れるのも、体調を整え、疲労回復につながります。
おすすめの運動メニューについては、こちらの記事でも紹介しています。
「疲れを取る6つの方法!短時間ですっきりできるストレッチも解説!」
まとめ

50代男性の疲れがとれない原因として、ストレスや睡眠の質の低下、食生活の乱れ、脳への負荷などがあげられます。
これらの要因に対処することで、疲労回復が期待できます。食事や運動を見直し、より良い睡眠環境を整えることが重要です。
疲れの軽減や睡眠の質をサポートする製品の活用も、ぜひ検討してみてください。