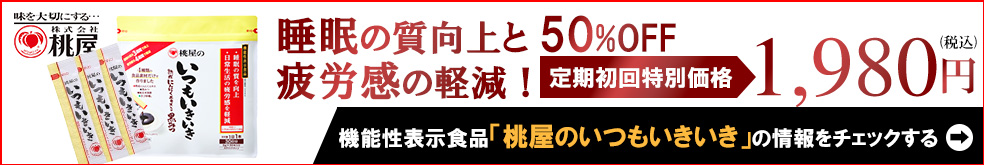朝にやる気が出ない原因4選

朝にやる気が出ない原因は、実は私たちの生活習慣や体調と深く関係しています。代表的な4つの原因をチェックしていきましょう。
体内時計の乱れ
1つ目は、体内時計の乱れです。
私たちの体には、24時間周期で繰り返される「概日リズム」という体内環境のリズムが存在します。これは体内時計によって調節されており、睡眠や覚醒、体温の変化、ホルモンの分泌などの生理的な働きをコントロールしているものです。
体内時計は約25時間周期で動いているため、24時間の概日リズムとの間に1時間ほどのずれが生じてしまいます。
通常、このずれは朝の光を浴びることで自然と修正されますが、夜更かしや不規則な生活習慣によって光を浴びるタイミングが乱れると、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌リズムも崩れてしまうことになります。
結果として、朝のやる気が出にくい状態に陥ってしまうのです。
特に現代社会では、夜間のテレビ視聴やスマートフォンの使用など、体内時計を乱す要因が増えています。
エネルギー不足
2つ目は、エネルギー不足です。朝起きたとき、脳はエネルギー不足の状態にあります。
脳の唯一のエネルギー源であるブドウ糖は、夜間の脳の活動によって消費され、朝には枯渇してしまうのです。
この状態で朝食を抜くと、エネルギー不足が続くため集中力が低下し、イライラしたりボーっとしたりしてしまいます。
脳は大量のブドウ糖を貯蔵できないため、定期的な補給が必要不可欠です。
ストレス
朝のやる気が出ない原因の3つ目は、ストレスによる影響です。
同じ仕事であっても、ストレスの少ない環境と多い環境では、作業効率や疲労度に大きな差が生じます。
自分に合わない仕事を強制されたり、裁量権が制限されたりする状況では、ストレスが蓄積してモチベーションが著しく低下してしまうでしょう。
近年では、実生活での人間関係だけでなく、SNSを通じたコミュニケーションによるストレスも増加傾向にあります。
疲労蓄積
4つ目は、心身の疲労の蓄積です。疲れは、私たちの身体が発する重要なアラームです。
過度な活動を続けることで蓄積した心身への負担に対して、休息の必要性を伝える警告といえます。
疲労が蓄積すると、朝起きるのがつらい、全身がだるい、やる気が出ないといった症状が表れます。
また、集中力の低下や食欲不振、肩こりなど、さまざまな不調のサインが出てくることもあるでしょう。
疲れが溜まる原因としては、働きすぎや睡眠不良、栄養の偏り、ストレスなどが考えられます。
朝からやる気を出すための最強ルーティン

これまでに解説した原因に対する、具体的な対処法を紹介します。
日々の生活に取り入れることで、朝のやる気不足を改善し、充実した1日を過ごしましょう。
決まった時間に起床する
前日の就寝時間が遅くなると、つい起きるのが遅くなってしまう方もいるでしょう。
しかし、起床時からやる気を出すためには、毎日できるだけ決まった時間に起床することが大切です。なぜなら、体内時計の遅れをリセットできるチャンスは朝しかないためです。
平日・休日にかかわらず、毎日同じ時間に起きることで規則正しいリズムができ、スッキリ目覚めやすくなります。
朝に日光を浴びる
朝起きたときに、日光を浴びる習慣をつけましょう。
朝日に含まれる青色の光には、体内時計を24時間周期に調整する効果があります。また、日中にしっかりと光を浴びることで、セロトニンの分泌が促されます。
セロトニンは夜になると睡眠を促すメラトニンに変化するため、睡眠の質を高めてくれるのです。
一方で、夜遅くまでスマートフォンやテレビの画面を観ることは避けましょう。これらの機器から発せられるブルーライトは、体内時計を狂わせる原因となります。
コップ1杯の水を飲む
朝食の前に、まずはコップ1杯の水を飲みましょう。
朝一番に水を飲むことで就寝中に失われた水分を補給できるのはもちろん、腸がゆるやかに刺激されて便通も促されます。
また、水分補給によって胃腸が刺激されると副交感神経が高まり、自律神経がバランス良く働くようになるとされています。
朝食で糖質を摂取する
朝のやる気不足を解消するには、朝食で糖分を摂取することも大切です。
寝ている間に消費されたブドウ糖を補給することで、脳に必要なエネルギーを供給できます。
おすすめは、米やパンを主食とした朝ごはんです。消化と吸収がゆっくり進むという特徴があり、血糖値はなだらかに上がって長時間維持されるため、脳に安定的にエネルギーを供給できます。
また、ビタミンB群を同時に摂取することで、糖分をエネルギーに変換する効率が高まります。下記のような食品も積極的に取り入れましょう。
✓ ビタミンB1が含まれる食品:紅鮭、まいたけ、大豆、わかめ、たらこ など
✓ ビタミンB6が含まれる食品:ブロッコリー、モロヘイヤ、ドライバナナ、抹茶 など
✓ ビタミンB12が含まれる食品:しじみ、あさり、いわし、さんま、卵、チーズ など
参考:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
なお、朝食は起床後1時間以内に摂るのがおすすめです。
起きてから1時間以内に食べ物を口に入れることで、血糖を下げるホルモン「インスリン」が働きやすくなります。
その結果、少量のインスリンで自律神経のバランスが安定しやすくなるといわれています。
また、起床から1時間以内に朝食を摂ることで体内時計がリセットされ、日中の運動効率が上がるのもメリットのひとつです。
朝食をしっかり食べるためには、夕食の摂り方にも注意が必要です。夕食を食べ過ぎたり、遅い時間に摂取したりしないよう、規則正しい食生活を心がけましょう。
朝からやる気を出すための日常的な対処法

これまでに解説した原因に対する、具体的な対処法を紹介します。
日々の生活に取り入れることで、朝のやる気不足を改善し、充実した1日を過ごしましょう。
運動をする
適度な運動は筋肉量を維持し、疲れにくい身体づくりにつながります。
また、やる気を高めるテストステロンの分泌を促す効果や、ストレスの発散、リラクゼーション効果が期待できるのもメリットです。
激しい運動をする必要はなく、軽い運動でも効果は期待できます。例えばストレッチで筋肉をゆっくり伸ばすことで血流が改善され、酸素や栄養が全身に行き渡ることで疲労回復を促進するでしょう。
運動のタイミングも重要です。朝食後から昼食前の時間帯は、軽いウォーキングをおすすめします。
この時間帯の運動は、血糖値の調整や代謝促進に効果的です。
一方、有酸素運動や筋トレは15~19時が最適とされています。この時間帯は肺や心臓の働きが活発で、筋肉の柔軟性も高まっているためです。
質の高い睡眠をとる
朝のやる気を出すためには、質の高い睡眠をとることも重要です。
睡眠の質を高めるためには、湯船でゆっくり温まるのがおすすめです。
就寝2時間ほど前に38度程度のぬるま湯に浸かることで体温が上がり、ちょうどベッドに入るころに体温が下がり始めます。すると自然な眠気を誘い、質の良い睡眠につながります。
また、寝る前のマッサージやストレッチによって心身がリラックスし、副交感神経の働きが高まります。マッサージやストレッチで血流が良くなると冷えや筋肉のこわばり、痛みも和らぎ、寝つきも良くなるでしょう。
なお、寝る前のマッサージやストレッチは無理をせず、心地良いと感じる強さで行うことが大切です。
関連記事:
「よく眠れない…眠りが浅い人の特徴と原因、改善のポイント」
「睡眠の質を上げる食べ物とは?意識的に摂りたい栄養素を紹介」
食事を見直す
朝のやる気を引き出すためには、バランスの取れた食事で必要な栄養素を摂取することも欠かせません。
特に三大栄養素である炭水化物、脂質、たんぱく質は、身体のエネルギー源として重要な役割を果たしています。
また、見落としがちなのが、微量栄養素の摂取です。微量栄養素とは、微量ながらも人の発達や代謝機能を適切に維持するために必要なビタミン、ミネラル(無機質)を指します。
ビタミンB群は炭水化物をエネルギーに変換し、神経の働きを維持する働きがあります。
ビタミンDはテストステロン産生に関与し、ビタミンCは体調管理に重要です。
ミネラル類では、亜鉛が脳細胞の機能向上やたんぱく質合成に、鉄分は神経伝達物質の合成や貧血予防に役立ちます。
やる気を引き出すための食べ物については、下記の記事も参考にしてみてください。
「【体調別】元気が出る食べ物は?おすすめの栄養素やレシピも紹介」
サプリを併用する
毎日の食事で栄養素をしっかり摂取するのが理想ですが、忙しい生活のなか、栄養バランスを考えた食事を毎食用意するのは難しいこともあるでしょう。
そんなときは、サプリメントを活用するのもおすすめです。
「桃屋のいつもいきいき」は、睡眠と疲労感を同時にサポートする機能性表示食品です。抗酸化作用がある熟成にんにくエキスが酸化ストレスを減らし、睡眠の質アップ、疲労感の軽減をサポートします。
1日1回好きなタイミングで取り入れるだけなので、忙しい方も続けやすいのが特徴です。興味のある方は、下記から詳細をご覧ください。
まとめ

朝のやる気不足には、体内時計の乱れやエネルギー不足、ストレス、疲労蓄積といったさまざまな要因が関係しています。改善のためには、朝の日光浴や適切な朝食の摂取、運動習慣の見直し、バランスの取れた食事を心がけましょう。
なお、症状が長引く場合は、背景に病気が隠れている可能性もあるため、医療機関への相談を検討してください。