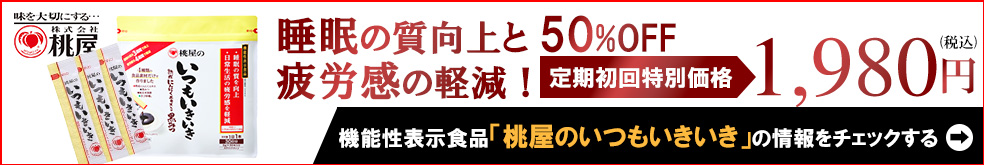あなたの「疲れ」はどのタイプ?

疲れには大きく3種類あり、それぞれ原因が異なります。異なるタイプの疲れが重なっているケースも少なくありません。まずは、3つの疲れについて詳しくみていきましょう。
関連記事:「朝起きた時が一番疲れているのは「自律神経」が原因!6つの対策をご紹介」
肉体的疲労
肉体的疲労とは、スポーツや長時間労働など、身体に負担がかかる肉体活動によって引き起こされる筋肉や全身の疲れを指します。
肉体的疲労と深い関わりがある物質として、乳酸があげられます。乳酸は、運動時にエネルギーが生成される過程で、筋肉に蓄積された糖が分解される際に発生する物質です。
乳酸の研究は発展途上にありますが、乳酸が発生する過程で筋肉のpHバランスが酸性に傾くことが肉体的疲労の原因の1つとして考えられています。また、筋肉のエネルギー源である筋グリコーゲンの減少も、疲れを引き起こす要因といわれています。
精神的疲労
精神的疲労とは、緊張やストレスが継続することで生じる疲れのことです。脳の使い過ぎが原因といわれており、集中力の低下やイライラを引き起こしやすくなります。
心と身体は密接に関係しているため、精神的疲労が身体の疲れとなって表れることも少なくありません。年齢を問わず発生し、子どもでも精神的疲労を感じることがあります。
神経的疲労
神経的疲労とは、視神経の使い過ぎや脳の緊張が続くことで生じるだるさやぐったり感のことで、「中枢性疲労」とも呼ばれています。
テレビやPC、スマートフォンなどの情報機器が普及した現代では、日常生活で大量の情報を処理するため、神経的疲労を溜め込みやすいといわれています。
疲れを溜めやすい方の特徴
誰しも疲れは感じるものですが、特に次のような特徴がある方は、疲れが溜まりやすい傾向があります。
女性
女性は一生を通じてホルモンバランスの影響を受けるため、疲れやだるさを感じやすい傾向があります。
女性が感じる疲れやすさの主な原因を紹介します。
貧血
女性の疲れやだるさの原因の1つに、貧血があげられます。
女性は月経によって血中の鉄が失われやすく、男性に比べて不足しがちです。さらに、妊娠中、授乳中は、通常よりも多くの鉄を必要とします。
鉄は、酸素を運ぶ役割のあるヘモグロビンの材料となる栄養素です。体内の鉄が不足すると血液中のヘモグロビンが減少し、全身への酸素供給が低下します。
その結果、身体が酸欠状態となり、疲れを感じるのです。
精神的な不調
強いストレスや不安など、メンタルヘルスの不調を抱えていると、疲れを感じやすくなります。
特に、妊娠や出産、育児、介護などのライフステージの変化にともない、精神的な不調を経験することが多く、その影響で疲れが身体に表れやすくなります。
女性ホルモンの減少
ホルモンバランスの変動が大きい時期に、疲れを感じやすくなることがあります。例えば、月経前は女性ホルモンの変動が激しく、疲れや眠気を感じやすくなります。
また、女性ホルモンが減少する閉経前後の10年間も、より一層疲れを感じやすくなる時期です。
一般的に、閉経は45歳~55歳ごろといわれていますが、女性ホルモンは30歳前後から徐々に減少します。そのため、30代後半を過ぎると、疲れが気になり始める方が増えるようです。
50歳以上
50歳を超えると、加齢の影響で疲れを感じやすくなります。これは、下記のような身体の変化が関係しています。
体力の低下
持久力や筋力、バランス感覚など、さまざまな要素から構成される体力は日常生活に欠かせない要素です。
人の体力は20歳を境に低下し始め、50歳を過ぎると急激に衰える傾向があります。それにともなって疲れやすさを感じることが増えます。
加齢による体力の低下は避けられないものの、日々の過ごし方次第で、体力低下の度合いやスピードを抑えることは可能です。具体的な方法については、記事後半で解説します。
自律神経の老化
自律神経は、性別に関係なく加齢とともに老化するといわれます。自律神経のはたらきが衰えると、血流のコントロールがうまくいかなくなり、疲れが出やすくなったり、回復が遅くなったりします。
疲れを溜め込まない身体を維持するために、自律神経を健やかな状態にし、年齢に応じた機能を保つことが大切です。
疲れを溜めない方法1.睡眠編

疲労回復の鍵を握るのが睡眠の質です。
疲労回復に役立つ「成長ホルモン」は、本来寝入ってから2〜3時間後に分泌されますが、睡眠の質が悪くなると十分に分泌されません。ここからは、睡眠の質を高めるコツを解説します。
起床後に太陽の光を浴びる
起床後に太陽の光を浴びると、睡眠の質が高まります。
人間には体内時計がありますが、1日あたりの周期が24時間より1時間程度長いといわれています。放っておくとどんどんずれてしまい、睡眠にも影響しかねません。
体内時計のずれをリセットし、24時間周期と合わせることで、生活のリズムが整えられます。さらに体内時計をリセットすることで、夜になると睡眠を促すホルモンであるメラトニンが分泌されやすくなり、質の良い睡眠がもたらされます。
体内時計をリセットするには、朝起きたときに太陽の光を浴びるのが有効です。
深部体温を下げる
自然な眠気は身体の内部の温度(深部体温)が下がるときに訪れ、睡眠時には深部体温が約1℃下がります。
深部体温を良いタイミングで低下させるには入浴が効果的です。お風呂に入ると一時的に体温が上昇しますが、血管が拡張して熱が放散されやすくなることで深部体温は下がります。一般的に入浴は寝る1~2時間前が良いとされています。
副交感神経を優位にする
夜の入眠前には、副交感神経を優位にする必要があります。
副交感神経を高め、リラックスするには深呼吸やストレッチが効果的です。
また、交感神経を刺激しないことも大切です。スマートフォンやテレビなどは交感神経を働かせてしまうため、就寝前の使用や視聴は控えましょう。
より詳しい就寝のコツを知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。
「寝れない時の8つの対処法とNG行動!寝たいのに寝れないのはなぜ?」
上記の方法を試してもよく眠れないという方は、サプリメントを活用するのもおすすめです。
「桃屋のいつもいきいき」は、睡眠の質の向上や疲労感の軽減に役立つ「熟成にんにくエキス」を配合した機能性表示食品です。
精神的ストレスなどの負荷がかかると、体内で活性酸素が発生し、酸化ストレスが蓄積され、睡眠の乱れや疲れを引き起こします。「熟成にんにくエキス」には抗酸化作用があり、酸化ストレスを軽減することで睡眠の質を向上させ、疲労感の軽減につながります。
寝ても疲れが取れない方や、毎日忙しくぐっすり眠りたい方は、ぜひお試しください。
関連記事:「何もしてないのに疲れるときは「活性酸素」が原因!?疲れを溜めない生活習慣とは」
疲れを溜めない方法2.食事編

睡眠に加え、食事も疲労回復に欠かせない要素です。次に、疲れにくい身体をつくるための食事の摂り方について解説します。
1日3食よく噛んで食べる
胃腸機能が低下していると、食べ物の消化や吸収がうまく行われず、栄養不足に陥って疲れや倦怠感を感じやすくなります。
胃腸の機能を高めるためには1日3食、よく噛んで食べることが大切です。
咀嚼することで唾液や胃液の分泌が促され、消化吸収機能が活発化します。
また、1日に必要な栄養を一度に摂取すると、胃腸に負担がかかったり血糖値が急激に変動したりするため、3食に分けて摂る必要があります。
ビタミンB群を摂取する
疲れにくい身体をつくるためには、ビタミンB群を摂取するのが効果的です。
身体のエネルギー源になる3大栄養素(「炭水化物」「脂質」「たんぱく質」)は、体内で消化され、エネルギーを生み出すための「TCAサイクル(クエン酸回路)」という代謝経路に取り込まれます。
これをうまく機能させるために必要なのがビタミンB群です。この栄養素が不足すると摂取した栄養をエネルギーにうまく変換できず、疲れやすくなります。
ビタミンB群が含まれる食品は下記のとおりです。
● 豚のヒレ肉(ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12)
● 鶏のむね肉(ビタミンB6)
● 赤身の魚(クロマグロの場合:ビタミンB6、ビタミンB12)
● 納豆(ビタミンB2、ビタミンB6)
● ごま(ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6)
● バナナ(ビタミンB6)
● 卵(ビタミンB2、ビタミンB12)
疲れやすい方は、積極的にビタミンB群が含まれる食材を摂るようにしましょう。
~豆知識~ 疲れのタイプ別の摂取したい栄養素
疲労には、肉体的疲労や精神的疲労、神経的疲労といった種類があります。疲労の種類によって、積極的に摂取したい栄養素は異なるため、自分の疲れの種類にあった栄養素を意識して摂るようにしましょう。
肉体的疲労には:たんぱく質など
長時間労働やスポーツ後などの肉体的疲労の回復には、たんぱく質が必要です。たんぱく質には、肉体的疲労で傷んだ筋肉を修復するはたらきがあります。
たんぱく質には、肉や魚などの動物性と豆類などの植物性があり、どちらもバランス良く摂る必要があります。疲れているときは、豆腐や納豆など消化の良い食品がおすすめです。
精神的疲労には:抗酸化ビタミン(ビタミンA、C、E)、カルシウムなど
ストレスなどの精神的疲労にはビタミンA、C、Eやカルシウムなどが効果的です。
ビタミンA、C、Eは、緑黄色野菜やフルーツに多く含まれており、増え過ぎた活性酸素を取り除く抗酸化作用があります。
カルシウムには神経系の過剰な反応を抑制し、イライラや過緊張を和らげる作用があります。疲労回復効果を高めるためには、マグネシウムと一緒に摂るのがおすすめです。
神経的疲労には:ブドウ糖、DHAなど
仕事や勉強で脳が疲れているときには、ブドウ糖やDHAを摂るようにしましょう。
ブドウ糖は体内に吸収されやすく、即効性のあるエネルギー源であり、疲労回復に役立ちます。摂り過ぎると血糖値の急激な変化につながるため、注意しましょう。
DHAは脳神経のはたらきを助け、記憶力や判断力を高める作用があります。さらに、血流を改善し、精神を安定させる効果も期待できます。
疲労回復に効果がある食べ物やレシピを知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
「精のつく食べ物とは?疲れ知らずのスタミナをつけよう!」
「睡眠の質を上げる食べ物とは?意識的に摂りたい栄養素を紹介」
疲れを溜めない方法3.運動編

疲労回復には、適度な運動も効果的です。デスクワークなどで長時間筋肉を動かさないと、血行不良が起こり、疲れやこりが悪化することもあります。
続いて、疲労回復につながる運動について解説します。
作業の合間に身体を動かす
身体を動かさない時間が続くと、筋肉に緊張が生じて血行が悪くなり、疲れを感じます。これを防ぐためには、作業の合間に意識して身体を動かすことが大切です。
また、PCやスマートフォンを長時間操作していると、首を前に突き出す姿勢や、両肩を前にすぼめる姿勢になりがちです。このような姿勢が長く続けば、首から肩の筋肉に緊張が生じ、疲れを感じてしまいます。
その対策として、作業の合間に首を後ろにゆっくり反らせたり、肩を回したりして、筋肉の緊張をほぐすことが効果的です。
入浴後にストレッチする
ストレッチをするなら入浴後がおすすめです。入浴後は血行が良くなって筋肉の緊張が緩み、柔軟性が高まっているため、身体がほぐれやすくなります。
肋間筋を伸ばすストレッチ
同じ姿勢で長時間作業していると、肋骨の周りの筋肉「肋間筋」が固まり、呼吸が浅くなってしまいます。呼吸が浅くなると不安や緊張につながりやすいため、不眠や疲れが取れないなどの症状につながります。
足を肩幅に開いて前で手を組み、身体を伸ばしたり左右に倒したりしてみましょう。肋間筋がほぐれると呼吸が深くなり、疲れにくくなります。
足の付け根を伸ばすストレッチ
座った姿勢が続くと、足の付け根まわりに老廃物がたまるため、足の付け根を伸ばすストレッチもおすすめです。ストレッチにより身体に溜まった老廃物をリセットすることで、足のむくみやだるさを解消できます。
足を前後に開き、前の膝を90度に曲げて後ろの膝が床につくまで上体を落としていく「ランジストレッチ」を取り入れてみましょう。
関連記事:「疲れを取る6つの方法!短時間ですっきりできるストレッチも解説!」
まとめ
疲れには、肉体的疲労や精神的疲労などの種類があります。病気ではないからといって身体に向き合わずにいると、疲れが慢性化してしまいます。
疲労回復には、睡眠の質を向上させてしっかりと休養を取るのはもちろん、食事や運動などの生活習慣も大切です。日々の生活を見直して疲れにくい身体をつくっていきましょう。