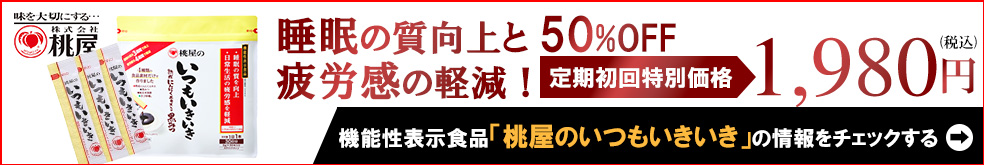朝起きたときが一番疲れている主な原因は「自律神経」

朝起きたときのだるさや疲労感は、自律神経の乱れが大きな原因です。
これは、自律神経が生活環境や体調の変化に敏感に反応する性質をもつからです。まずは、自律神経について簡単に解説します。
自律神経とは
自律神経とは、呼吸や血液循環、消化などを調整する神経のことです。ストレスや環境の変化に応じて体内を微調整し、生命活動を維持する役割を担っています。そして、自律神経は自分の意思で動かすことはできません。
自律神経には交感神経と副交感神経の2種類があり、それぞれ異なるはたらきをします。交感神経は運動時や日中の活動時に優位になり、血管を収縮させて血圧や心拍数を上昇させます。
一方、休息やリラックスをするときにはたらくのが副交感神経です。夜間や安静時に副交感神経が優位となり、血管が拡張して血圧や心拍数が低下します。
自律神経の乱れにつながる5つの要因

ここでは、自律神経の乱れを引き起こす5つの要因を紹介します。
1|季節の変わり目(春バテ・秋バテなど)
季節の変わり目は、自律神経が乱れやすい時期です。
例えば春は寒暖差が激しく、身体が環境に適応しようと交感神経が優位になります。その結果、疲れやだるさを感じやすくなり、「春バテ」を引き起こすことがあります。
また、春は低気圧と高気圧が頻繁に入れ替わることも、交感神経、副交感神経の切り替えがうまくいかなくなる原因の1つです。さらに、春は新生活が始まる時期でもあり、環境の変化による緊張やストレスも自律神経の乱れにつながります。
秋から冬にかけても憂うつな気分になりやすく、「秋バテ」「冬季うつ」などといわれます。脳内の神経伝達物質「セロトニン」には自律神経のバランスを整える作用がありますが、秋から冬にかけて日照時間が短くなるとセロトニンの分泌量が減少してしまうのです。
その結果、自律神経のバランスが乱れやすくなると考えられています。
2|生活習慣の乱れ
身体には体内時計が備わっており、自律神経のバランスを調整する役割を果たしています。
夜になると体温や血圧、脈拍が低下し、朝から昼に上昇するという生体リズムを生み出すのも体内時計の役割です。睡眠不足や昼夜逆転など不規則な生活を送ると生体リズムが乱れ、体内時計も狂ってしまいます。
その結果、自律神経のバランスも乱れやすくなります。
3|ストレス
精神的、身体的なストレスも自律神経が乱れる原因の1つです。
ストレスを受けると交感神経が刺激され、身体が活発な状態を維持しようとします。通常、交感神経が高まった後には副交感神経が優位になり、リラックスモードへ切り替わります。
しかし、ストレス状態が続くと副交感神経への切り替えがうまくいかず、自律神経が乱れてしまうのです。
4|ホルモンバランスの変化
女性の場合、ホルモンバランスの変化も自律神経に影響を与えるとされています。
更年期には、女性ホルモンの「エストロゲン」「プロゲステロン」の分泌が減少し、ホルモンバランスが大きく崩れます。
特に、エストロゲンの急激な減少はホルモン分泌の指令を出す脳の視床下部にも影響を与え、自律神経の調整がうまくいかなくなるのです。
5|天候の乱れ
晴れの日は交感神経が優位になりやすく、くもりや雨の日は副交感神経が優位になりやすいといわれています。そのため、気圧や気温の変化が大きいと自律神経も乱高下しやすくなるのです。
また、気温や気圧の急激な変動は身体的ストレスとなり、自律神経に影響をおよぼすと考えられています。
朝の疲れを解消するための対策6つ

自律神経を調整するには、体内時計が重要なポイントです。体内時計には中枢時計と末梢時計があり、視床下部にある中枢時計が交感神経と副交感神経をコントロールしています。
不規則な生活を続けたりストレスが蓄積したりすると、この中枢時計がずれてしまうのです。その結果、自律神経のバランスが崩れ、朝のだるさや疲労感が出てきます。
したがって朝に疲れを残さないようにするためには、生活習慣の改善が重要です。体内時計を適正な状態に保つ生活を心がけ、自律神経のバランスを整えていきましょう。
生活リズムを一定にする
自律神経を整えて朝の疲れを解消するためには、起床、食事、就寝などの生活リズムを一定にすることが大切です。
特に起床時間には気を配りましょう。寝る時間より起きる時間の方が体内時計に与える影響が大きいため、前の晩の就寝が遅くなっても、できるだけ朝の起床時間をずらさないようにします。夜更かしは避け、早寝早起きを心がけるのが理想的です。
また、食事を抜いたり時間を遅らせたりなど、食事のリズムの崩れは体内時計の乱れにつながります。食事の時間に2時間以上のずれが生じないよう注意し、規則正しい食生活を心がけましょう。
朝日を浴びる
自律神経をコントロールする中枢時計は、目から入る光の刺激でリセットされます。
朝起きたら、まずカーテンを開けて窓から入る太陽の光を浴びるようにしましょう。光を部屋に取り入れることで、脳が目覚めやすくなります。
中枢時計のリセットにより自律神経も整うため、疲労感の解消にもつながります。
朝日で体内時計をコントロールし、すっきりとした気持ちで1日をスタートさせましょう。
起床して1時間以内に朝食を摂る
朝の疲れを解消するためにも、朝食を摂るようにしましょう。糖質の摂取によって血中のインスリンが増えるのを合図に、体内時計が調整されます。
また血糖値を高めるホルモンは、朝5時前後から分泌が盛んになります。朝6~7時ごろに起きて1時間以内に朝食を摂るとインスリンの効率が高まります。
朝ごはんのメニューは、インスリン分泌を促す糖質と、一緒に摂ることでエネルギー代謝が活性化し体内時計のリセット効果がアップするたんぱく質を含む食材を選びましょう。
米やパンなどの主食や、グラノーラなどは糖質を豊富に含みます。朝から摂取しやすいたんぱく質を含む食材としては、卵やヨーグルトなどがおすすめです。
日中はたくさん太陽を浴びる

朝の疲れを解消するためには、睡眠ホルモンとも言われる「メラトニン」の分泌をコントロールすることも重要です。
メラトニンは睡眠と覚醒のスイッチを入れる役割をもち、光の刺激によって分泌量が変化します。
例えば、昼間は太陽光を浴びることで、メラトニンの分泌が抑えられます。一方で、夜間は本来、太陽光を浴びないためメラトニンが多く分泌され、眠気を誘発するのです。
日中は積極的に外の光を浴びてメラトニンの分泌を抑えましょう。外での運動や、昼休みの散歩もおすすめです。
寝る直前にスマートフォンを使用する習慣があると、眠れない、起きるのがつらいなどの症状が表れがちです。夜は液晶の強い光を避けてメラトニンの分泌を促すことで、質の高い睡眠を確保しましょう。
光とメラトニンの密接な関係を意識した体内時計の調整も、朝の疲れ対策として重要です。
深呼吸する
ストレスが溜まりやすいと感じている場合は、気づいたタイミングで深呼吸してみましょう。深呼吸によって、脈拍が落ち着く、血圧が下がるなど副交感神経の働きが活発になります。
具体的には、鼻からゆっくり5秒かけて息を吸い、口から10秒かけて吐く「1対2の呼吸法」が効果的です。これを2〜3分間続けると、感情や思考が安定してリラックスできるようになります。
また、ため息も自律神経に良い影響があります。大きく「はぁ〜」と息を吐くことで、自然と深呼吸ができるようになります。
朝の疲れ解消のためには意識的に深呼吸する習慣をつけ、日ごろのストレスに対処しましょう。自律神経を整える上で、呼吸法は手軽で効果的な手段といえます。
睡眠不足にならないようにする
体内時計を整えるためには、睡眠も大切です。睡眠不足は自律神経の乱れを招き、朝の疲れの原因となります。できるだけ夜更かしを避け、早寝早起きを心がけましょう。
また、睡眠は時間も大切ですが、質も非常に重要です。十分な睡眠時間を取れていても、日中に眠気を感じるような場合は質が良くない可能性が高いでしょう。
睡眠の質を高めるコツは、就寝1時間前までに入浴を済ませておくことです。入浴によって体温を上昇させ、体温が下がりリラックス状態になるころに布団に入ることで、質の高い睡眠が得られます。
普段から眠りの浅さが気になる方や、睡眠の質が悪いと感じている方は、サプリメントを活用するのも1つの手段です。
「桃屋のいつもいきいき」は、S-アリルシステインを豊富に含む「熟成にんにくエキス」を配合した機能性表示食品で、睡眠の質向上や疲労感の軽減に役立ちます。
寝ても疲れが取れない、朝のしんどさを感じている方は、ぜひお試しください。
まとめ
朝起きたときのだるさは自律神経の乱れが原因の可能性があります。
規則正しい生活リズムを心がけ、栄養のある食事、十分な睡眠を意識することが大切です。また、体内時計や自律神経を整えるには深呼吸や日光浴もおすすめの方法です。
今回紹介した6つの対策を生活に取り入れ、朝からすっきりとした1日を過ごしましょう。