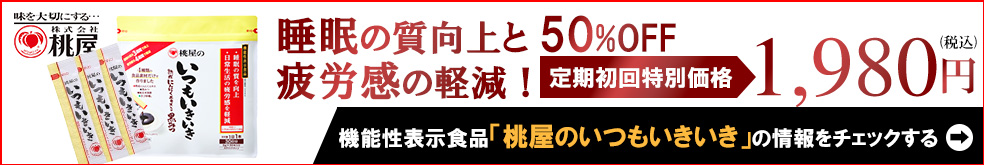目次
夜中に目が覚める「中途覚醒」とは

中途覚醒とは、眠りが浅く夜中に目が覚めて再度眠るのが困難な状態をいいます。
通常、最も深い眠りは入眠後約3時間の間に訪れ、朝が近づくにつれて徐々に眠りが浅くなっていきます。
中途覚醒の場合、入眠後間もなくの時間帯には眠れるものの、睡眠が浅くなるそれ以降の時間帯に途中で目が覚めてしまうことから、睡眠不足や眠りの質の低下が避けられません。
中途覚醒をはじめ、寝つきの悪い「入眠障害」や、早朝に目が覚めて二度寝ができない「早朝覚醒」といった不眠状態が続くと、倦怠感、意欲低下、集中力低下、食欲低下など、身体に不調が生じることもあるため注意が必要です。
不眠の原因はストレスや体内時計の乱れ、室内環境など、生活に関係するものが多くあげられます。
そのため、睡眠の質を高めるには、自分自身の生活習慣を振り返り、不眠の原因を理解した上で、改善を図ることが必要です。
夜中に目が覚める「中途覚醒」の原因
まずは、夜中に目が覚めてしまう中途覚醒や早朝覚醒が起こる原因をみていきましょう。
ストレス
睡眠に関するトラブルは、精神面も大きく関係します。
ストレスや疲労が溜まると、自律神経が乱れたり、悩みごとであれこれと考えて脳が興奮状態になったりするため、眠りにくくなるのです。
加齢
加齢に伴い、睡眠は浅くなる傾向にあります。
健康な方でも、年をとるにつれて深いノンレム睡眠が減り、浅いノンレム睡眠が増えるようになります。ちょっとした物音や光などで目が覚めてしまう方は、加齢による眠りの浅さが原因かもしれません。
寝室の環境
就寝環境が睡眠を阻害することもあります。例えば、騒音や光などの刺激が気になったり、寝室の環境(温度、湿度)や寝具が合わなかったりすると、安眠できません。
また、深部体温は寝ている間に下がり続け、目覚めに向けて上昇していきます。エアコンのタイマーをかけて寝ている場合に、タイマーが切れて室温が上昇すると、同時に体温が上がり、目が覚めてしまうこともあります。
アルコール
アルコールの摂取は眠気を促す一方で、入眠から約3時間以降はノンレム睡眠で得られるはずの深い眠りが阻害されることが知られています。
ノンレム睡眠とは、大脳が休息した状態の睡眠段階で、疲労回復にも関与しています。朝起きたときに熟睡感や睡眠への満足感を得るためにも、ノンレム睡眠で深く眠ることが重要です。
たとえ睡眠時間を6時間以上確保していたとしても、アルコールを摂取していると、入眠後約3時間以降の眠りが浅くなってしまいます。睡眠時間の半分以上で良質な眠りが得られない可能性も否めません。
加えて、アルコールには利尿作用もあるので、尿意をもよおして中途覚醒が増えることも考えられます。
カフェイン
覚醒作用のあるカフェインも、寝つきを悪くさせる原因のひとつです。睡眠効率の悪化に大きく影響するといわれており、ベッドで横になっている時間よりも、実際の睡眠時間が大幅に少ないといったことも起こり得ます。
また、アルコールと同じく利尿作用もあるため、尿意で夜中に目覚めてしまう原因にもなります。
夜にぐっすり眠るための対処法6選【生活編】

次に、睡眠の質を高め、夜にぐっすりと眠るための対処法を紹介します。
夜中に目が覚めたときに、またスムーズに眠りにつける方法を知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
「寝れない時の対処法3選!不眠の原因や睡眠の質を高める方法も詳しく解説」
規則正しい生活を心がける
睡眠や覚醒のリズムは体内時計で調整されるため、就寝と起床の時間は毎日なるべく同一時刻にして、体内時計を整えることが重要です。
週末の夜更かしや昼寝のしすぎは、体内時計が乱れる原因になるので注意しましょう。日中に眠気がある場合は、午後3時までに30分以内の昼寝をとることをおすすめします。
早寝しようと、眠気がないにもかかわらず早めに寝床に入るのは逆効果なので注意してください。寝つきが悪くなり、中途覚醒が増えてしまいます。
運動を習慣的に行う
睡眠の質を上げたいときには、ウォーキングやサイクリング、水泳などの有酸素運動を継続してみましょう。運動習慣がある方は不眠になりにくいことが知られています。
うっすらと汗をかく程度の有酸素運動であれば身体への負担が軽く、「きつくて続けられない……」といったことも避けられるのではないでしょうか。1回のみの激しい運動は、継続が難しいだけでなく、かえって睡眠の質の低下を招くといわれています。
睡眠に効果的な運動のタイミングは、夕方~夜にかけてです。就寝の約3時間前が目安とされています。運動で脳の温度を一時的に上げることで、就寝時に脳の温度が大きく下がり、スムーズな入眠をもたらします。
寝る前のスマートフォンを控える
寝る前にスマートフォンを長時間使用すると、睡眠の質を落としてしまいます。ブルーライトには睡眠を促すメラトニンの生成を抑制する作用があるため、寝つきが悪くなるのです。
また、強い光を感じると脳が昼間だと勘違いして、眠れなくなることもあります。
布団に入ったらスマートフォンの電源を落とすようにするなど、ルールを決めておくのがおすすめです。
ぬるめのお湯にゆっくり入る
入浴時、湯船につかる習慣は睡眠の質を高めるといわれています。スムーズな入眠には、副交感神経の働きが優位になり、身体の深部体温が低下することが欠かせません。
ぬるめのお湯で身体をじっくりと温めると、自律神経は心身ともにリラックス状態になる副交感神経が優位になります。
加えて、深部体温が一時的に上がり、その後ゆっくりと下がっていきます。結果として就寝時の深部体温が低下し、寝つきが良くなって睡眠の質も高まる仕組みです。
入浴に適したタイミングは、就寝の2~3時間以上前です。38℃程度のぬるめのお湯に25~30分浸かることをおすすめします。
就寝前の熱いお湯での入浴は、交感神経が優位になるので避けたほうが良いでしょう。
寝室の環境を見直す
ベッドや布団、枕、照明など、寝室の環境を自分に合ったものに見直すことも重要です。
寝室の環境は室温20℃前後、湿度は40~70%に保つのが良いとされています。エアコンは、暑いと感じたら冷房を使用し、蒸し暑さを感じたときや梅雨の時期は除湿にすると良いでしょう。
室内の湿度は変化しやすいので、自動調節機能のある加湿器などを使用するのもひとつの手です。
出典:「不眠症」(e-ヘルスネット)
寝具を適切なものに変える
安眠のためには寝具にもこだわりたいところです。枕は後頭部から首にかけてのすき間を埋める役割があります。首や肩への負担を軽減し、心地良い眠りにつけるように、自分の体型に合った安定感のある枕を選ぶことが大切です。
ベッドマットや敷布団は、適度な硬さのものを選びましょう。柔らかすぎると、背骨が曲がりやすく、腰痛の原因になります。背中や腰をバランス良く支え、楽な姿勢を保ちやすい寝具がおすすめです。
睡眠中は汗をかくなどして身体から熱が奪われやすいため、吸湿性や放湿性の高い寝具を選ぶこともポイントです。
【栄養学の博士監修】夜にぐっすり眠るための対処法3選【食事編】

夜中に目が覚めてしまう睡眠の悩みは、食事の内容やタイミングと深く関係していることがあります。
ここでは、栄養学の博士の視点から、快眠をサポートするための食事のポイントを解説します。
毎日決まった時間に朝食を摂る
朝食は、一日が始まるサインとして心と身体を覚醒させてくれます。体内時計の調節に役立つため、毎日決まった時間に朝食を摂ることが重要です。朝食は、糖質とたんぱく質を含むバランスの良い献立を心がけましょう。
忙しい朝も手軽に糖質をとれる食べ物として、ごはん、パン、シリアルなどがおすすめです。たんぱく質の多い食べ物には、肉、魚、乳製品、納豆、豆腐などがあります。
これらの食材を組み合わせて日中の活動に必要なエネルギーを朝食で摂取し、昼は活動して、夜はゆっくりと休む生活リズムを整えていきましょう。
夜の食事に気を付ける
夕食は、就寝の2時間前までに済ませて、腹八分目に抑えることが大切です。寝る前の食事は、消化活動によって睡眠が妨げられてしまいます。特に脂肪分の多い食事は消化に時間がかかるため、早めに夕食をとりましょう。
トウガラシやこしょうなどの香辛料は交感神経を刺激する作用があるため、就寝前の摂取は控えましょう。カフェインが含まれるコーヒーや緑茶、チョコレートなども覚醒作用があることから、就寝の5~6時間前から控えるのが好ましいです。
先に述べた通り、アルコールは寝つきを良くするものの、明け方の睡眠を妨げるため、適度な量を飲むようにしましょう。
アルコール代謝能力の低い日本人では、適度な飲酒量としてはビール500ml、清酒180ml程度といわれています。また、アルコールの代謝も時間がかかるため、就寝の4時間前までにお酒を飲み終えましょう。
寝る前に温かい飲み物を飲む
睡眠の質を高めるには、身体を内側から温める飲み物を取り入れるのも効果的です。一時的に深部体温を上げた後、ゆっくりと下がっていく過程で、眠気が出てきます。
例えば、ハーブティーには心身を落ち着かせる作用があり、就寝前の飲み物としておすすめです。中でもカフェインを含まないカモミールティーは睡眠を妨げにくいため、夜中や就寝前でも安心して飲めます。
また、ホットミルクも身体を温める効果が期待でき、就寝前のリラックスタイムにピッタリです。牛乳に含まれるカルシウムには交感神経の興奮を抑える働きがあり、心地良い眠りをサポートしてくれます。
夜中に目が覚めたときの過ごし方
夜中に目が覚めたとき、無理に寝ようとするとかえって目が冴えてしまい、さらに眠れなくなることもあります。ここでは、中途覚醒時に心身を落ち着かせ、再び自然に眠りにつくための過ごし方を紹介します。
ゆっくりと深呼吸をする
夜中に目が覚めても焦らず、まずはゆっくり深呼吸してみましょう。
深呼吸には副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる働きがあります。自律神経のバランスが整うことで、再び眠りにつきやすくなるとされています。
■おすすめの呼吸法
床や布団の上に仰向けになり、手足を大きく広げて大の字になりましょう。息を吐くときは、身体がゆっくりと床に沈み込んでいくようなイメージをもちます。息を吸うときは、身体が軽く浮き上がるようなイメージで行うのがポイントです。
「寝なきゃ」と気にしすぎない
夜中に目が覚めたとき、無理に寝ようと焦ったり不安になったりすると、交感神経が刺激され、かえって眠りから遠ざかってしまいます。大切なのは、ゆったりとした気持ちで過ごすことです。
「一生このまま眠れないわけではないし、大丈夫」と、自分をなだめるように声をかけてあげることで心が落ち着き、再び眠りにつきやすくなります。
リラックスのツボを押す
身体を無理に動かさず、布団の中で手軽にできるセルフケアとして、ツボ押しもおすすめです。ここでは、リラックスに役立つ2つのツボを紹介します。
場所:頭のてっぺん、両耳の上端を結んだ線と、鼻の延長線が交差するあたり
効果:精神的不安をやわらげ、心を落ち着かせる働きがあるといわれる小指を除いた4本の指先や手のひらを百会にあて、息を吐きながら5秒程度かけて、心地良いと感じる程度にゆっくり押しましょう。押した後は、軽く息を吸います。この流れを数回繰り返すことで、リラックス効果が期待できます。
場所:手のひらを軽く握ったとき、人差し指と中指の先端の間にあたる部分
効果:精神に働きかけ、心を穏やかにする作用がある反対の手の親指の腹にツボをあて、息を細く長く吐きながら、5秒程度かけて心地良いと感じる程度に押しましょう。このとき、身体の中の余分なものを吐き出すようなイメージをもつのがポイントです。次に、ゆっくりと息を吸いながら指を離します。この一連の動きを、10回程度繰り返しましょう。
睡眠にお悩みの方におすすめのサプリメント

生活習慣の改善に加えて、良質な睡眠を補助するサプリメントの摂取もおすすめです。「夜中に目が覚めてしまう」「眠りにつきにくい……」といった方にぜひおすすめしたいのが、「桃屋のいつもいきいき」です。
機能性表示食品である「桃屋のいつもいきいき」は、S-アリルシステインなどのにんにく成分を含む熟成にんにくエキスを配合しています。
S-アリルシステインは、熟成したにんにくに含まれるアミノ酸の一種で、生のにんにくにはごくわずかしか含まれていません。
臨床試験(ヒト試験)では、「桃屋のいつもいきいき」が中途覚醒を減少させることで、睡眠の質が向上することが確認されています。
また、摂取12週間後の睡眠の質向上と、摂取後4週間での日常生活で生じる疲労感の軽減が確認され、ダブルの機能性が科学的にも実証されています。「気持ちが前向きになった」「元気が出てきた」などのうれしい声もいただいております。(※)
参照:
届出の詳細につきましては、以下URL(消費者庁ホームページ)より届出番号欄に「H986」と入力して検索し、ご確認ください。
消費者庁「機能性表示食品検索」
熟成にんにくエキス、黒みつ、純玄米黒酢、きび砂糖®の4つの食品素材のみを使用しているため、まろやかな甘みがあるのも特徴です。ホットミルクやヨーグルトに混ぜたり、ドレッシングの材料にしたりなど、普段の食事に取り入れられます。
健康的ではつらつとした毎日を過ごしたい方は、ぜひお試しください。
※調査期間:2020年6月〜2021年8月、調査対象:定期購入3回以上のお客様、N=620、77.2%の方が「満足」「やや満足」と回答
夜中に目が覚めるのが続く場合は?
年齢を重ねると深い眠りが減り、わずかな振動や物音などの刺激で目が覚めやすくなりますが、これは加齢による自然な変化です。
夜中に目が覚めても再入眠でき、日常生活に支障をきたしていない場合は、過度な心配は不要です。
一方で、慢性的な中途覚醒は生活習慣病のリスクを高める可能性があるといわれています。十分な休息がとれず、日常生活に支障が出ている場合や、中途覚醒が長く続いて気になる場合は、受診を検討しましょう。
まとめ
中途覚醒を減らして睡眠の質を高めるためには、規則正しい生活、食事時間、寝る前の習慣、寝具などを見直すことが重要です。
生活習慣の見直しとあわせて、良質な睡眠をサポートしてくれる「桃屋のいつもいきいき」もご検討ください。
食事だけでは摂取することが難しいS-アリルシステインが豊富な熟成にんにくエキスをたっぷりと摂取できるので、睡眠の質向上と日常生活で感じる疲労感の軽減が期待できます。
【この記事の監修者:長田裕子】
株式会社桃屋 研究開発部

資格:博士(栄養学)、食生活アドバイザー2級、品質管理検定1級、アロマテラピー検定1級
情報の信頼性について:
当記事の「【栄養学の博士監修】夜にぐっすり眠るための対処法【食事編】」「おすすめのサプリメント」に関する情報は、博士(栄養学)の監修のもとで作成しています。専門的な知見に基づき、正確かつ実用的な情報提供を心がけています。加えて、社内チェック体制により、表現の適切性・正確性についても多重に確認しています。